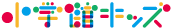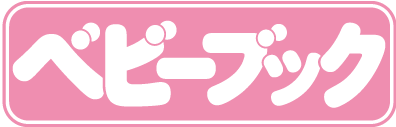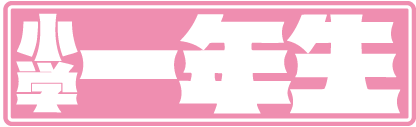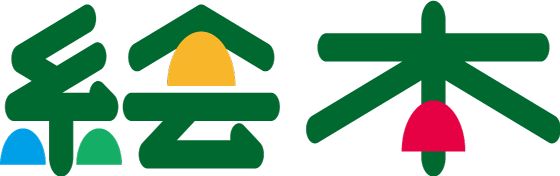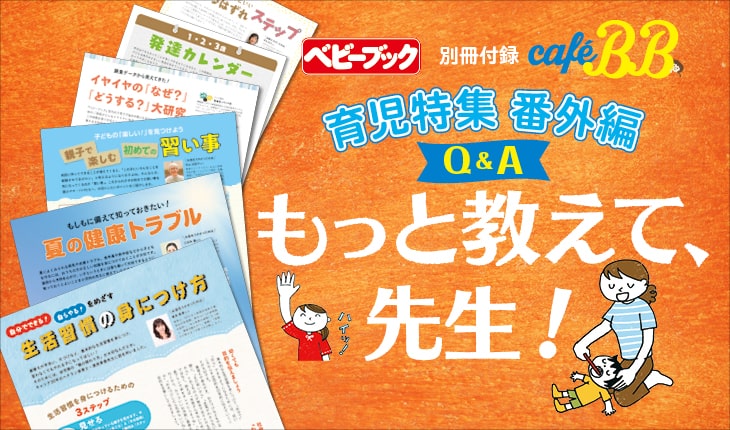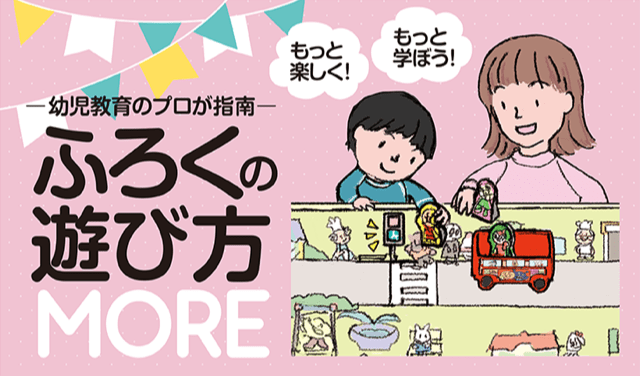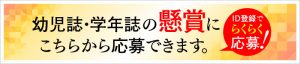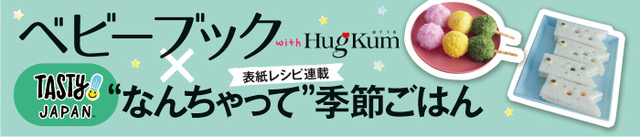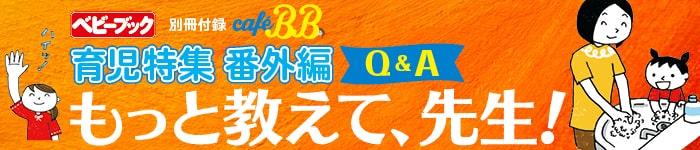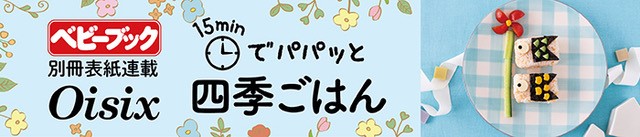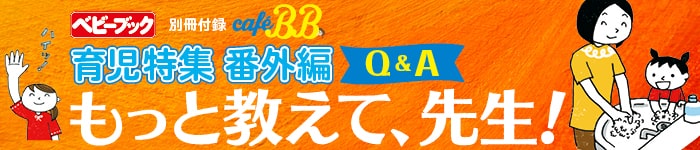
おうちの中でも、ちょっと目を離したすきに起ってしまう、1・2・3歳児のけがや事故。特に重大な事故につながりかねない危険や、気をつけておきたいポイントについて、小児救急の専門家がアドバイスします。

Q.3 6歳と2歳のきょうだいです。特に気をつけたほうがいいことを教えてください。
Q.4 料理していると子どもがキッチンに入ってこようとします。どのようなことに気をつければいいでしょうか?
Q.5 ベランダや庭でプール遊びをする際に気をつけることを教えてください。
Q.6 帰省先での事故防止のために特に気をつけることはありますか。
Q.1 家の中で一番危険な場所はどこでしょうか?

A.
消費者庁が2020年に行った調査によると、最も多く事故が起こった場所はキッチンで、次にリビング、階段と続きます。
重篤な事故が起きやすい場所としては、浴槽とキッチン、ベランダや窓付近が挙げられます。
ただし、ここだけに限らず、対処をしていないと家中どこでも幼児にとって危険がある場所だと認識しておくことが大切です。
Q.2 テーブルの上に置いたあった薬の数が目を離したすきに減っていました。もしかしたら子どもが間違って飲んでしまったかもしれませんが、飲んでいないかもしれません。この場合、受診したほうがいいでしょうか?
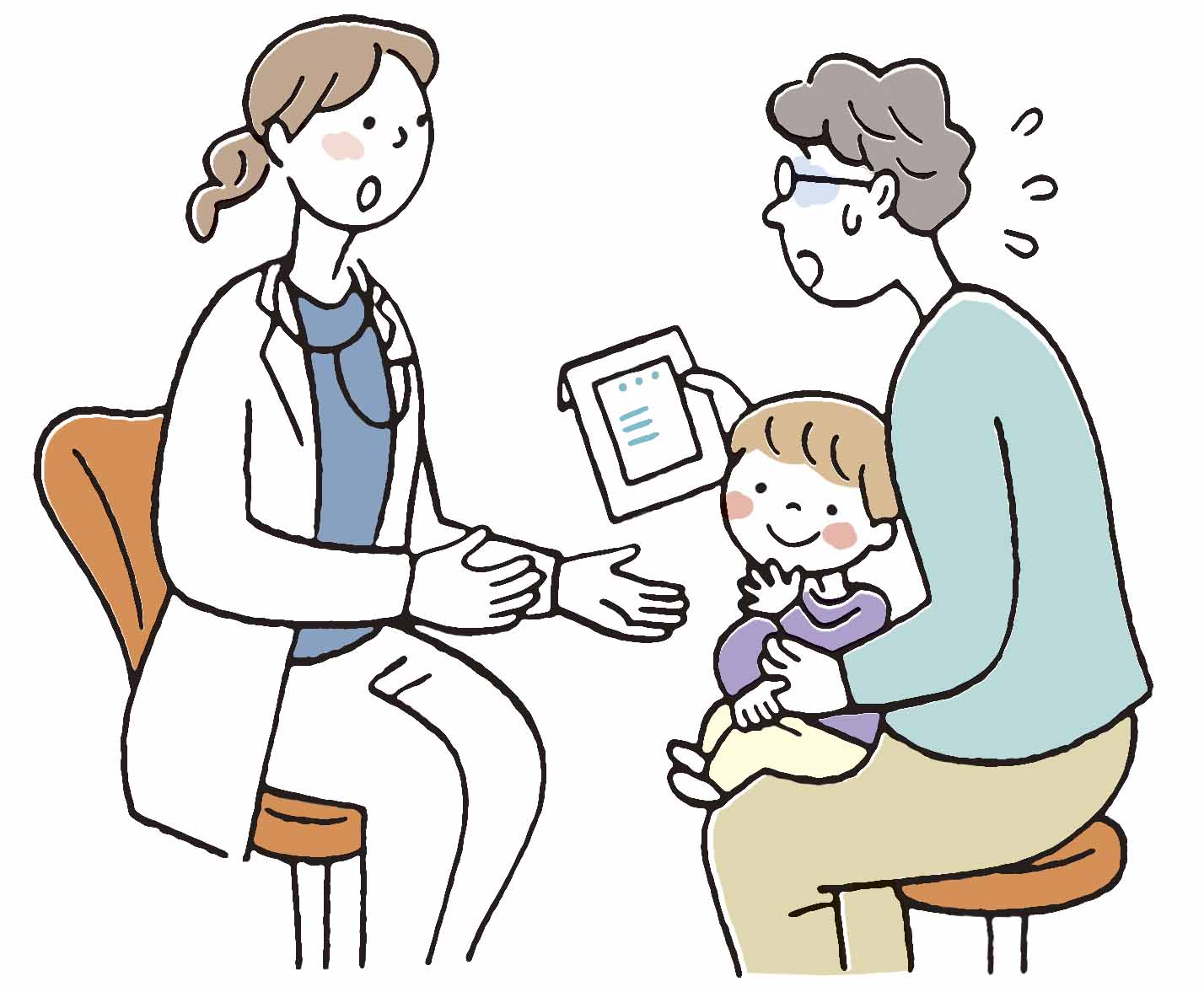
A.
飲んだか飲んでいないかわからないということですが、わからないのであれば基本的には受診しましょう。もし飲んでいなかったのであれば、「飲んでいなくてよかったね」となるだけのことですので、受診をためらう必要はありません。
薬の中には、「ワンピルキャンキル」と呼ばれる、1錠でも死に至らせる薬があります。受診の際は、飲んだ可能性がある薬を持参してください。
「ワンピルキャンキル」
- 血糖降下薬
- Ca拮抗薬
- 三環系抗うつ薬
- 抗精神薬
- オピオイド
- ロペラミド
- 血管収縮薬(α作動薬)入り点鼻薬
- 外用消炎剤 (サリチル酸)
Q.3 6歳と2歳のきょうだいです。特に気をつけたほうがいいことを教えてください。
A.
上の子用のおもちゃには小さいパーツのものがあるので、一緒に遊ぶと下の子が誤飲する危険性があります。きょうだいで一緒に遊ぶ際は、できれば下の子の対象年齢に合わせたおもちゃで遊びましょう。上の子のおもちゃで遊びたい場合は、時間や空間を分けるように配慮を。
Q.4 料理していると子どもがキッチンに入ってこようとします。どのようなことに気をつければいいでしょうか?
A.
キッチンは事故が起きやすい、危険が高い空間なので、入れないようにすることを第一に考えましょう。ベビーゲートは予防策として効果が高いというエビデンスがありますので、幼児期はなるべく設置しましょう。キッチンの構造上、ゲートをつけることができない場合は、リフォーム業者など、設置を専門とする業者に相談してみるのもいいでしょう。
Q.5 ベランダや庭でプール遊びをする際に気をつけることを教えてください。
A.
「タッチスーパービジョン」という言葉があります。これは、「手の届く範囲でひと時も目を離さず見守る」という意味です。子育て中だからといって全ての瞬間を「タッチスーパービジョン」の状態でいるというのは難しいものですが、必ず「タッチスーパービジョン」で見守らなければならないときもあります。それが、プールや入浴など、水に関連している時間です。
プール遊びをしている間は、すぐに手が届く範囲で子どもに集中して見守る必要があります。他のことをしながら見守る、ではいけません。
水遊びするわが子がかわいいから動画を撮って、SNSに投稿……と目を離すのもNG。撮るだけなら構いませんが、投稿する作業は後にしましょう。それほどまでに、プールやお風呂は一瞬の隙に危険が生じてしまう場所なのです。
Q.6 帰省先での事故防止のために特に気をつけることはありますか
A.
一番気をつけてほしいのは薬です。Q.2で紹介した「ワンピルキャンキル」は、高齢の方が飲んでいる薬が多いのです。これらの保管場所について、祖父母だけに任すのではなく、ママパパも一緒に再度確認しておきましょう。1.5m以上の位置で子どもの目に入らない場所に置いてあれば安心です。
他にも、ポットや炊飯器などの家電が床に置かれているなど、幼児が過ごすのに適した環境になっていないことが多いので、帰省したらママ、パパが一度家の中を見回って、危険がないかをチェックするようにしましょう。

植松悟子先生
国立成育医療研究センター副院長、救急診療科統括部長。北里大学医学部卒業。小児科専門医・指導医、救急科専門医、麻酔科標榜医、DMAT隊員、災害時小児周産期リエゾンなどの資格を持つ。
イラスト/さいとうあずみ 文/洪 愛舜 構成/KANADEL
おうちの中での事故は、環境づくりと大人の配慮によって、その多くが予防できるものです。『ベビーブック』2024年8月号「&ベビー」では、起こりやすい事故の例やその予防策について詳しく解説しています!

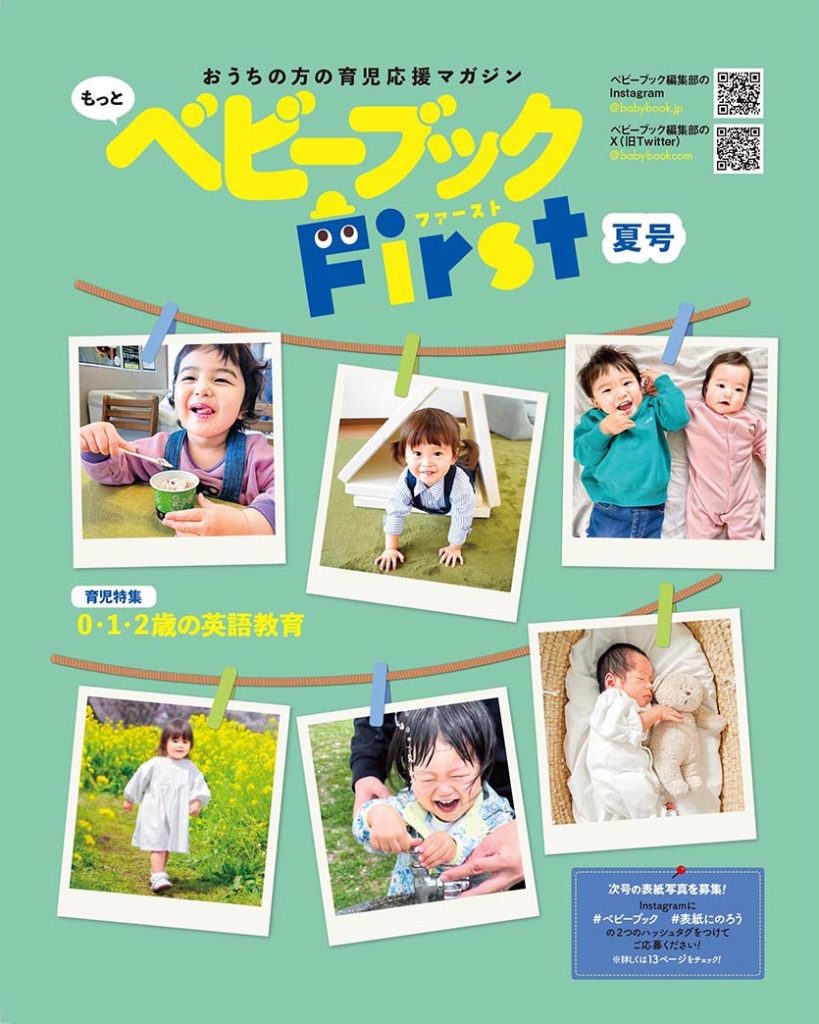
育児特集 番外編Q&A【もっと教えて、先生!】全記事リストはこちら